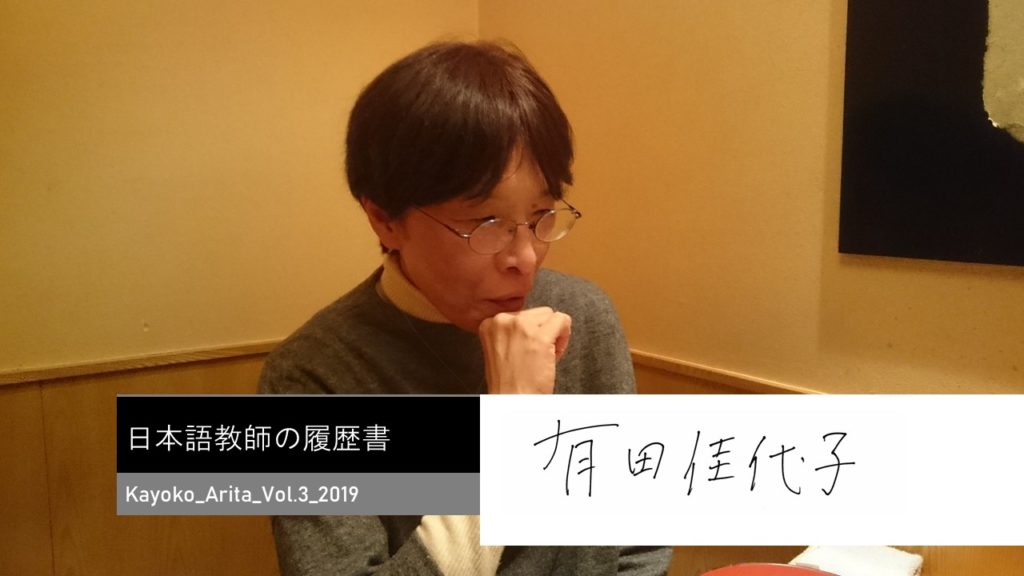
マジョリティに働きかける、立場を超えて対話する
今回は大学で教員をされている有田佳代子さんです。2019年1月26日、新潟駅構内のレストランで昼食を食べながら、和やかな雰囲気のなか、約2時間お話をうかがいました。ご自身のキャリアを「黒歴史」と謙遜されつつ、若い日本語教師に伝えたいことがあるとインタビューを引き受けてくださいました。
《今回の「日本語教師」》有田佳代子(ありた・かよこ)さん 新潟大学グローバル教育センター准教授。2019年3月まで敬和学園大学人文学部特任准教授。公立学校教員退職後に無資格日本語教師となり、その後大学院(ともろもろの紆余曲折☆)を経てゆるゆる更新中。今のところの関心のありかは、日本語教育史、言語政策、日本語教師のキャリア形成。主著は『多文化社会で多様性を考えるワークブック』(共編著/研究社)、『日本語教師の「葛藤」 (構造的拘束性と主体的調整のありよう)』(ココ出版)、『心ときめくオキテ破りの日本語教授法
』(共著/くろしお出版)、『会話の授業を楽しくするコミュニケーションのためのクラス活動40―初級後半から上級の日本語クラス対象
』(共著/スリーエーネットワーク)。
「日本人にもっと働きかけていきたい」
―現在のお仕事
瀬尾ま 今(=インタビュー時)の職場の敬和学園大学には、何年ぐらいいらっしゃるんですか。
有田 もう長いですね。15年くらいかな。
瀬尾ゆ 15年の間で、どうですか。
有田 小さい大学なので、日本語教育を専門にしている教員は私だけなんですね。だから、すごく自由に、やりたいことをやりたいようにやってきちゃった感じですね。
瀬尾ゆ やりたいことを、どういうふうにやってこられましたか。
有田 基本は授業です。「こういう授業が必要ですからやらせてください」みたいな。留学生だけのクラスじゃなくて、日本人学生も一緒に取れるクラスにして、それはすごくよかった。
瀬尾ま けっこう自由に自分のやりたい授業ができるんですか。
有田 そうですね。ただ、授業とか業務とかが多くなって、自分で自分の首をギュウギュウ絞めてしまっている感じでもあるんだけど(笑)。
瀬尾ま 自分で首を絞めているけれども、それでもやるモチベーションは何ですか。
有田 楽しいしおもしろいけど、忙しいですよね。忙しいけど、おもしろいし、やったほうがいいかなという思いかな。私たちは日本語教育の専門家ですけど、「日本語教育学って何か」っていうところだと思うんですね。「日本語教師は外国人に効率よく日本語を教えていく人たち」っていうイメージがあって、それが世間から素朴に私たちに期待されていることですよね。もちろんそれはそれできっちりやらなきゃいけないことだと思うんです。でも、それだけだと圧倒的に足りないっていうか。やっぱり私たち日本語教師はマジョリティである日本人に働きかけていかないと、私たちの仕事は全然完結しない。もともとの顧客の非母語話者のためにも、外国から来た人たちのことをわかっている私たちが日本人にもっと働きかけていかなきゃいけないんじゃないかっていうのは、とても思うんですね。
瀬尾ゆ 日本人に働きかけるというと?
有田 日本社会でという限定ですけれども、まだ声をあげられない学習者の人たち、外国から来た人たちがたくさんいて、その人たちがどんな状況にいるのかを私たちはわかっているわけだから、一時的に代弁していくとか。そして、これからは海外に出ていくにしても、日本にいるにしても、外国の人たちと一緒に生きていかざるを得ない社会じゃないですか。そうしたときに、私たち日本語教師は文化的背景が違う人たちと日常的に接しているから、これをやるともっと互いにわかり合えるとか、言っちゃいけないこととか、そういうセンスって普通にできてくるんじゃないかと思います。たとえば、「やっぱり日本が1番だよね。アジアでは……」とか、「だから〇〇人はダメだ……」とか、けっこう普通に言っちゃう人いますよね。そういう時に、お茶の間でも「それはおかしいよね」とか、「お父さんどうしてそういうふうに思うの?」みたいな感じで話していけるような力って、むずかしいけど、これから必要だと思うんです。
瀬尾ゆ うーん。
有田 たとえば、日本語学校の先生にしても、外国人に日本語を教える仕事だけではない仕事もあるように思います。非母語話者に日本語を教えるだけでは仕事の場も広まらないし、若い人たちがどんどん入ってこられる職業には、なかなかならないんじゃないかなと思うんです。だから、何らかの形で日本人に働きかけていかなきゃいけないっていうのは、すごく思いますね。だけど、それはそれで仕事量がいっぱいになっちゃって大変ですよね。
瀬尾ゆ それが業務の一環になればいいんですよね。今は日本語を教えるっていうのがベースにあって、有田さんがおっしゃったようなことはプラスアルファでしないといけない仕事になってる。でも、それがそもそも日本語教師の仕事として認められて、例えば半分は日本語を教えて、半分はそういう仕事をしてくださいみたいなポジションがいっぱいあれば、自分の仕事の範囲内でできるわけですよね。
有田 まさに! おっしゃるとおりだと思います。そうなったら、自分で自分の首を絞めるようなことにはなりませんよね。そういう方向に、わたしたちは動いていくべきだなと思います。
そして、たとえば敬和学園大学に日本語教師になれるコースがあるって聞くと、国際社会で活躍するみたいなキラキラとしたイメージが日本語教育に対してあるから、女の子たちなんかが「じゃあ、敬和に入ろう」みたいな、ちょっとこう惹きつけるようなところがありますよね。でも、結局は日本語教師になる人って本当にごく一部。だったらむしろ、コースの名前を「多文化なんとか」みたいにしたほうがいいのかなと。ただ、そうするとキラキラとしたイメージがなくなって結局は誰も学生が来なくなっちゃうという声もあります(笑)。でも、先生になるだけじゃなくて、この社会でこれから生きていく上で、絶対に必要な力だよっていうことを、もうちょっと上手にアピールすることができたらいいのかなと。
瀬尾ゆ 日本語教育を学んで身につくのは、日本語の教え方だけじゃないってことですね。
瀬尾ま 今、敬和学園大学ではどんなクラスを担当されてるんですか。
有田 半分は留学生に対する「日本語」の授業です。そして、日本人も留学生も両方が取れる「日本語表現」っていう演習の授業と「日本事情」の授業ですね。あとは「日本語教育学概論」。これは日本人のほうが多いかな。その辺のクラスでは、割と今言ったようなことを話したりしてます。あと、別の大学で180人ぐらいのクラスで「多文化共生論」的な授業をやっていて、手話の話とか、やさしい日本語の話とか、外国人って誰のことなのか、日本人って誰のことなのか、みたいなことも話しています。それが、私たち日本語教師の得意分野なんですよっていうこととか、日本語教育学を学ぶとこういう力がつきますよっていうことを、もっと言っていかないといけないと思っています。

「『これに向かって!』みたいなことが、あまりなかった」
―日本語教育に向き合うまで
瀬尾ま そもそも日本語教師の道には、どのようにして進まれたんでしょうか。
有田 はっきり目標を持って「これに向かって!」みたいなことが、私の人生ではあんまりなくて。その時々の成り行きっていうか、その場その場で面白いなって思ったことをしたり、そこしか進む道がないから仕方なくっていう感じで日本語教師の道に進みましたね。
瀬尾ゆ もともとは違うお仕事をされていたんですか。
有田 大卒後、公立中学校の社会科の教員を5年くらいしていました。高校生とか大学生の時に、中学校の先生になろうって思って教員になったんです。でも、最初の3、4日で「あっ間違えた」って思って(笑)。
瀬尾ま え、どうしてですか。
有田 子どもたちとの関わりはいいんですけど、「上履きを踏まないで」とか、「制服のスカートはここまで」とか、そういう生活指導がもうだめだと思っちゃって。授業は面白くて一生懸命やってたんですけど、大学時代に勉強してなかったから自分にストックがないって思ったんですね。それで、大学のときの友達3人で一緒に教員になったんですけど、その人たちと「いいよね、辞めて」って、軽々しく辞めちゃった感じ。で、他の仕事もなさそうだし、どうしようかなって思って、とりあえず大学に行ってみるかみたいな感じで大学に入りました。
瀬尾ま 大学院ですか。
有田 じゃなくて、その時は学部に編入しました。
瀬尾ゆ 学部に戻られたのは、どうしてなんですか。大学を卒業してたから、大学院でもいいのかなと思ったんですけど。
有田 全然勉強していなかったので、大学院は頭になかったんですよね。そこら辺も全然思慮がないって感じですね。「なんで学部なの?」ってみんなに言われました。
瀬尾ま 新しく大学に入って日本語教育を勉強されたんですか。
有田 違うんです。それが、社会学。だから、結局なんでもよかったっていうか。それで、学部に戻ったときにアルバイトを探したんですけど、時間的に日本語学校で働くのがよかったんです。当時は日本語教師の資格がなくても、教員の経験だけで採用されちゃった。大学を卒業した後も別の日本語学校に移って、最初そこで非常勤で働いて、その後専任になりました。
瀬尾ま じゃ、大学卒業時点では、日本語教師になりたいって気持ちがおありだったというわけではなく?
瀬尾ゆ できることをつないでいったら、日本語教師になってた、みたいな?
有田 そんな感じです。面白くなくはなかったけど、すごく情熱を持って、というのでもなかったかな。「専任になりませんか?」、「じゃ、やります」みたいな感じだったと思います。それに、経済的にもちょっと安定するし。でもボーナスなんて本当、公務員の時に比べたら、「え?」みたいな感じでしたけど(笑)。
瀬尾ゆ お仕事のほうは、どうでしたか。
有田 周りの先生たちが優秀で、今も付き合ってるんですけど、みんな頑張ってる人たちばっかりで、楽しかったですよね。先生たちはすごく勉強してたし。でも、非常勤の時のほうが面白くて、専任の仕事が嫌になったというか。中学校教師の時の経験から学んでいないんですね。授業をするのは面白いけど、他の事務的なこととかがめんどうになってしまって。たとえば、非常勤の先生たちに「こんなふうにやってください」、「それはだめです」って、その理由が自分でもよくわからないのに言わなくちゃいけなかったり。あと、クラス数とか学生の人数とか、経営的なことも考えないといけないし。今考えれば、専任はやらなきゃいけないんですけど。それに、主任の先生と大げんかしちゃって。それでプライベートなことも関係して日本語学校を辞めて、その少しあとでベトナムに行くことにしたんです。
瀬尾ま なぜベトナムに?
有田 ねー。それもすごくいい加減で。ベトナム行き自体はやはりプライベートマターが理由でしたが、「日本語教師やりませんか」という募集を新聞で見たんですね。そこは学習者の半分ぐらいが今の技能実習生、当時は研修生と言っていたんですけど、研修生を日本に送り出すっていう機関でした。でも、それだけじゃない学生もいたんですけれどもね。
瀬尾ゆ ベトナムはいかがでしたか。
有田 面白かったですね。よかったと思います。私、初級が苦手なんですけど、そこではちゃんと初級に向き合ったなっていう。
瀬尾ゆ 向き合うっていうのはどういうことですか。
有田 東京の日本語学校の時は中上級が多くて、基本的に直接法でやってたんです。でも、ベトナムでは、最初は英語を使って、その後はけっこう一生懸命ベトナム語を勉強して、ベトナム語を使って教えました。でも、「初級に向き合った」とは言えないか。
瀬尾ま じゃ、ベトナム語もできるんですか。
有田 当時はけっこうできて、日本に帰ってきてから国際関係学の修士課程に入ったんですけど、そこではベトナム語の資料を使って、当時の研修制度について修士論文を書きました。
瀬尾ま ベトナムから帰ってきて、修士課程に入られたんですね。
有田 そうです。ベトナムで3年やって、「なんかもう飽きちゃった」みたいな(笑)。でも、やっぱり何もなく帰るとちょっとまずいかなと思って。そんな時に、早稲田大学のアジア太平洋研究科のことを知って、ベトナム語がある程度できるようになっていたし、ベトナムについて全然知らないのにベトナムで仕事をしていたから、ベトナムについて勉強したいなって。それも本当、先のこと何も考えてないんですよ。で、戻ってきて、修士論文を泣きながら書いて。本当に泣いた(笑)。本当にきつかったですね。で、修士論文を書くのが精いっぱいで、日本語教育は全然勉強しなかったんです。今になれば、なんでだろうって思いますね。
瀬尾ゆ ご興味としては国際関係のほうが強かったってことなんでしょうね。
有田 そうですね、その時は。でも、アルバイトでは専門学校で日本語を教えていたんです。で、修士論文を書き終わって、もうへとへとになっちゃって。その後の進路が全然決まってなくて、どうしようかと思って。で、研究したいことがはっきりしないのに、博士課程の入学試験を受けちゃって。そしたら落っこちますよね(笑)。落っこちちゃって、これからどうしようと思っていた時に雇ってくれたのは、やっぱり日本語学校だったんです。でも、残念ながらその時の学校では、ちょっと授業がうまくいかなかったかな。
瀬尾ま それはどうしてなんですか。
有田 どうしてなんだろう。うーん。そこで「やりなさい」って言われている教科書を進めるのがつらかった。授業やるのが、あんまり面白くなかったかな。で、「なんでだろう」と思ったら、やっぱりこれまでちゃんと日本語教育を勉強していなくて、ちゃんと日本語教育と向き合っていないからうまくいかないんだ、今までは経験だけで教えていて、いい学生たちだったから力技でなんとかやっていたんだ、と思って。だから、やっぱり日本語教育を勉強しなきゃと思って、その時に日本語教育学会に入ったんです。そして、日本語教育学会の研修に参加して、何人かの先生方にいろいろと教えていただき、そこで「そっかぁ!」と思って、そこら辺からちゃんと日本語教育に向き合うようになったかも。だから、それまではやはり向き合ってなかったんですよ。経験律だけでなんとなくやっていた。で、面白かったし、なんとなくできちゃった感じ。でも、最後に非常勤で1年働いていた日本語学校で全然うまくいかなくって、それで勉強しなきゃだめなんだって思ったかな。
瀬尾ゆ・瀬尾ま へー。
有田 日本語教育学会の研修は週1回とかのペースで、けっこう頻繁に行われて。でね、私たち5人くらいのクラスだったんです。
瀬尾ゆ 少ないですね。どういうことを勉強されていたんですか。
有田 アクションリサーチとか、構成的グループエンカウンターとか、ジャーナル書くとか、勉強しました。「そっかぁ、こういうことを日本語のクラスでやればいいんだ!」っていうのが、そのときわかったかな。
瀬尾ゆ 先ほどベトナムで初級に向き合ったっておっしゃっていたんですけど、ここでの日本語教育と向き合ったというのは、また違う次元なんですか。
有田 うーん、違う次元ですね。ベトナムでは、本当にしょうがなくて頑張ってやったって感じ。でも、今回のは、すごく遅すぎるんですけど、「私はやっぱり日本語教育でいこう」って、そこで決めたんです。それまでは、ことばを教えることの面白さっていうのが実はあんまりよくわかってなかったと思います。でも、日本語教育学会の研修を受けて、「そっか! これは面白いよね」っていうふうに、やっとわかった感じ。研修は、私にとってすごくありがたいことだったなと思います。あの研修に行けてよかったですよね。
瀬尾ま その研修の後に敬和学園大学に行かれたんですか。
有田 はい。一緒に研修を受けた人のなかに大学で非常勤講師をしている人もいて、日本語学校だけじゃなくて違うところでもできるよねって思った。で、「ここで募集あるよ」みたいに教えてもらって、じゃあ出してみようって応募して、敬和学園大学に。

「集まって少しずつでも話をしていく」
―日本語教師の葛藤が生み出される構造を変える
瀬尾ま 博士課程はどのタイミングで行かれたんですか。
有田 敬和学園大学でいろいろやって、論文とか書き始めてからです。経験はあるし、仕事も面白いんだけど、バックグラウンドになる知識がやはり足りないと思って。それで、今度こそ日本語教育学で学位とろうと思って。
瀬尾ま 博士論文は日本語教師の葛藤について書かれたんですよね。なぜこのテーマにたどりついたんですか。
有田 それはやっぱり、私自身が葛藤していたんです、いろいろ。葛藤してましたね。たとえば、私は1990年代からボランティア教室にも関わっているんです。東京の町屋日本語教室と新潟に来てからは新発田日本語教室のみなさんとも。ボランティアの人たちはとても力があって、すごく一生懸命にやってくださってるんですよ。うちの大学に初級のクラスがなかったときは、ゼロ初級レベルの人が勉強できるのはボランティアの地域の教室しかなかった。地域の外国籍住民のかたが科目等履修生として大学で日本語を学ぼうとするとき、ボランティアには優秀な方たちがいっぱいいるから、「すいません、お願いします」みたいに、こっちからお願いしてしまうこともありました。でも、ボランティアの人たちがいると、若い日本語教師のお給料は低くなっちゃうし、それとどういうふうに整合させたらいいのよ、っていう葛藤。学会とかでは、「ボランティアは教えてはだめ。ボランティアは交流活動だけにしましょうよ」っていう流れがありますよね。それはわかるし正しいとも思うんだけど、現実問題としては、なくなったら困っちゃう。地方ではほんとうに、ボランティア教室しかない、そこしか頼れないという場合が、まだまだ多いと思います。行政もボランティアのみなさんにべったり頼りっぱなしだし。これからもそういう状況が、少し続くのではないでしょうか。それはすごい葛藤でしたね。そこは、政策がずるいと思います。
授業中も日々葛藤がありましたよね。敬語や女性語や勉強したくない連中に「そりゃそうだよな」と思いつつ、「でも、ちょっとは敬語を知らなきゃいけないでしょ? 就職活動で女の子がオレはまずいでしょ?」とか言いながら、いつも葛藤していて。じゃ、博士論文のテーマはこれかなって。
瀬尾ま 2017年の言語文化教育研究学会の年次大会のシンポジウムで、葛藤についてお話しされていたと思うんですけれども。具体的にどんなお話だったんですか。
有田 この間、「高齢者は日本文化をよく知ってるし日本語も堪能だから、高齢者こそ日本語教師になったほうがいい」みたいな記事をFacebookで見て、「えっ!」って思ったんですよ。もちろん高齢者がやるのは全然問題ないと思うんです。高齢の方たちにとって、自己実現とか、やりがいになると思いますし。あるいは主婦の方たちは配偶者控除の103万円、130万円の壁とかあるじゃないですか。それ以上はちょっと働きたくないっていう。そうするとやっぱり、この仕事でしっかり食べていきたいっていう人たちと利害の対立があると思うんですよね。
あと、大学でも日本語学校でも専任の先生ってある程度、人事権を握ってますね。で、組織の論理もあるし、経営者的な立場にもならなきゃいけない。一方で、非常勤の先生たちは1科目授業がなくなるだけで、収入に大きな違いが出るわけです。だから、次の学期にもちゃんと授業がもらえるように、不満や疑問があっても黙ってしまうっていう。日本語教師同士に分断の状況、対話が成り立ちにくい状態がある。
また、アカデミズムのなかでも留学生関係部署の教員と他の専門の教員とでは、「格差」があったりしますよね。日本語教師が葛藤を抱く原因は、そこら辺にもあるのかなって思いますね。
瀬尾ま その中で私たちはどうしたらいいんですかね。
有田 ひとつには、やっぱり1人でいちゃいけないって思います。それこそ別の学校の先生でもいいし、同僚の先生でもいいし、日本語教師同士が、ネット上でもいいし、集まって少しずつでも話をしていくことが大事かなと思います。あの大学で教えている人とこの大学で教えている人とか、大学の先生と日本語学校の先生とか、ボランティアの先生とか、なんというか私たち分断されちゃっていますよね。やっぱり日本語の先生同士がバラバラになっちゃってるっていうのは、本当にまずいと思うんですね。
ただ、瀬尾さんたちのやってる日本語教師のネットワークの「つながろうねっト」とか、大阪の「土曜の会」とか、そういうつながりが今いろいろなところでできつつあるんですよね。ネット上でも、若い日本語の先生たちがTwitterを通じて、同じハッシュタグを付けて集まりましょうって言って、集まってる。それは10人とか20人とかで、そんなに規模は大きくないし、学会みたいに組織的なものでもないんですね。でも、だからこそ自主的だし、動きが機敏だし。「じゃあ、こっちでご飯食べちゃおっか」、「こっちで話しちゃおうか」、みたいに。他にも、「こんぶの会」という会も精力的にやってらして、頻繁に日本語の先生たちが集まってワークショップを開いたりしてる。私、こういうつながりは、すごく希望だなと思うんですよ。
瀬尾ま あちこちで日本語教師のつながりができてますよね。
有田 地域ごととか、ネット上とか、小さくてもいいからとりあえず集まって。いろんな考えがあるんだけど、「文型積み上げはほんとうにだめなの?」みたいなことを話す場っていうのが、やっぱり要るのかなと思うんですね。そこから、たとえば待遇のこととか働く環境のこととかもみんなで考えたり、あるいは交渉していく力になっていく場合もあるかもしれないと思います。それで、私たちもまだ3回しかしていないんですけれども、新潟で周りの人たちと日本語学校の先生とかボランティア教室の先生とか、立場を超えて、ブックレビューをしたり、みんなで話したりする活動をしています。

「日本人に発信する、いろいろな日本語教師と対話する」
-有田さんからのメッセージ
瀬尾ま 最後に、今から日本語教師になりたい人やキャリアの浅い人たちに向けてメッセージはありますか。
有田 これは反対意見も多いとは思うんですが、外国人の人たちへの日本語教育はもちろんなんだけど、それだけじゃなくて、日本人に働きかける方法を考える必要があると思います。たとえば、日本語学校で教えてる先生たちが留学生を連れて小学校に行こうとか、いろんなやり方があるように思います。地域の中で継続的になんかやりましょうとか。日本人に向けた発信っていうのは、必要かなって思います。そして、瀬尾(ゆ)さんがおっしゃるように、それを日本語教育機関や日本語教師の業務のひとつとして位置付けていくという、そういう動き方ができたらいいと思います。
そして、もう一つはやっぱり、何らかの形で周りともっとつながっていくことが大事だと思います。そんなこと言わなくても若い人たちはみんなやってるんですけれども、学校を超えて、立場を超えて、地域の人たちとか、それこそ「やりがい」を求める高齢者の人たちとも対話をしていく場を作っていく。それを作るのは私たちのようなおばさん系かなとは思ってるんですけれども、若い人たちもできればつながっていってくれたらいいなって思っています。
インタビューを終えて
瀬尾ま 私自身も日々モヤモヤとした葛藤を抱き、それが自分の原動力になっているところもあります。お話を伺いながら、有田さんが葛藤を抱え、それと向き合おうとする姿勢に共感しました。日本語教師たちの葛藤を共有できる場が求められているのかもしれません。そのような場を今後もさまざまな活動を通して創出していきたいなと改めて思いました。
瀬尾ゆ 明確な目標を持って「それに向かって!」ということがあまりなかったとおっしゃっていました。でも、心のどこかに引っ掛かりを感じたときに、勢いに任せてその気持ちに目をつぶるのではなく、ひとつひとつに丁寧に向き合ってこられたからこそ、日本語教師の「葛藤」というテーマと今の教育、新潟でのご活動につながっていると感じました。日々の仕事のなかで葛藤や違和感を抱いたら、それらを無いものとせず丁寧に向き合うことで生まれることがあるのだと思います。
