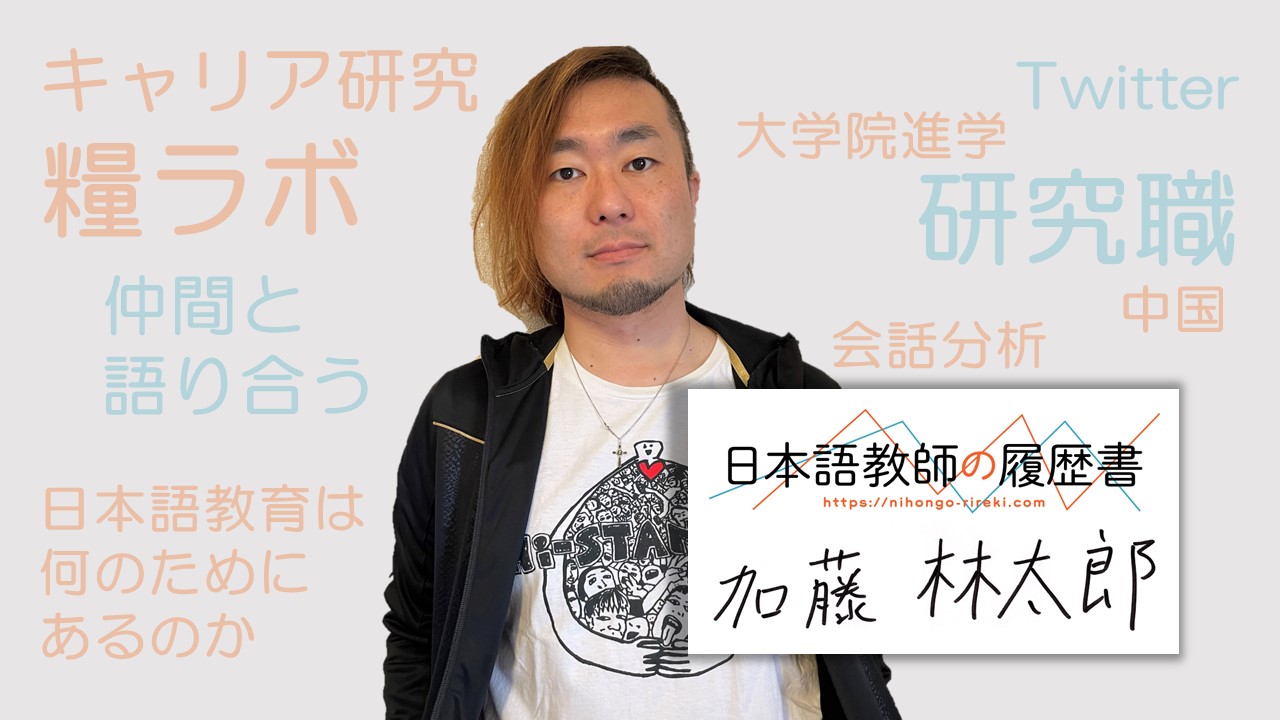
vol.22 「ここに仲間がいた、声を上げて仲間を作る、実践を通して社会を変える」加藤林太郎さん
今回は海外で教えられたあと、日本国内の日本語学校を経て現在は大学で教員をされている加藤林太郎さんです。2022年12月にZOOMでお話をうかがいました。
《今回の「日本語教師」》加藤林太郎(かとう・りんたろう)さん 神田外国語大学留学生別科講師。小学校時代の3年間をインドネシアで過ごしたことが原体験となり、高校のときに日本語教師を志す。京都外国語大学在学中に留学したオランダ国立南大学での教育実習で初めて教壇に立ち、卒業後、京都外国語大学の専攻科を経て、中国・吉林華橋外国語学院(現・吉林外国語大学)に赴任。そこで3年間を過ごし、名古屋大学大学院に入学するために帰国。博士前期課程修了後は日本語学校に専任として勤務し、3校目で教務主任に。その後国際医療福祉大学に移り、授業のほかに、留学生別科のコーディネート業務などにもあたる。研究面では、日本語教師のキャリア研究を行う「糧ラボ」を主宰するほか、教材開発、会話分析などの研究にも携わる。2022年4月より現職。Twitter : rintarock1980
「いつかインドネシアに帰りたいな」―日本語教師を目指す
瀬尾ま 日本語教師になろうと思ったきっかけを教えていただけますか。
加藤 僕、帰国子女なんですよ。父が国語の教員をしていてインドネシアのスラバヤの日本人学校に派遣教員として行くことになったので、僕も小学校3年生から5年生までそこにいたんです。日本人学校は、小学校1年生から中学校3年生までの全校児童生徒が40人ぐらいしかいなくて、家族みたいな中で過ごしていました。あと、父が教えるところも間近に見られて学校が非常に身近で、そこでの生活が非常に楽しかった。インドネシアという国自体も僕にすごく合っていたんですよね。
小学校6年生のときに日本に帰ってきたんですけど、いつかインドネシアに帰りたいなとずっと思ってたんです。親は「じゃあ、外交官かな」と言ってたんですけど、いやいやいやと思いながら(笑)。なんかないかなあと思っていたところに『ドク』というドラマがあって、菅野美穂が出てたんですよ。当時は菅野美穂が好きだったのでドラマを見て、日本語教師っていう仕事があるのを知りました。これだったらなれるかもしれないし、インドネシアに帰れるかもしれないなと思ったんです。
瀬尾ま 最初は日本語教師になるというよりも、インドネシアに帰りたいという気持ちが強かったんですか。
加藤 そうですね。インドネシアに帰る手段として日本語教師になろうという気持ちでした。
瀬尾ま 『ドク』を見たのは、中学生くらいの頃ですか。
加藤 高校生です。でも、正直に言うとドラマは1話しか見ていないんです(笑)。だから、ドクと先生がその後どうなったかは知りません。日本語教師という仕事を知れたから十分と思って(笑)。ドラマを見た次の日に進路指導室に行って、「将来の仕事」みたいな本で日本語教師を探したのをおぼえています。進学校に通っていたので、大学に行くというのは前提にありました。それで、専門として日本語を学べる大学はどこだろうと探して、進路を決めた感じです。日本語教育関係以外の学部は受けず、結果的に京都外国語大学に行きました。
「正直、これで日本語教師になれるのかな」―大学時代にインドネシアとオランダに
瀬尾ゆ 日本語教師に憧れを持って大学に入られたと思うんですが、大学での日本語教育の勉強はどうでしたか。
加藤 京都外大に行ってすごくよかったのは、同じような人たちが集まっていたっていうことです。結局は日本語教師にならなかった奴もいっぱいいるんだけど、同じような価値観を持った人がたくさんいて、その中にいられたのはうれしかったなと思います。あと、同じく京都外国語大学を出た小西達也さんが、入学してすぐに「日本語教師は食べていけない」と言われたという話を、この『日本語教師の履歴書』でしていたんですけど、まさに同じことを僕も言われました。これはこの大学の伝統芸なのかなと思っているんですけど(笑)。同級生は結構その言葉で思い悩んだみたいなんですけど、僕はあんまりシリアスにはとらえてなかったかもしれません。日本語教師と言われる人が実際にいるわけだし、なんらかの道があるだろうなと漠然と思ってたのかもしれないですね。
瀬尾ま へー。

加藤 ただ、僕は日本語教師になりたいと思ったけど、『ドク』も1話しか見てないし、日本語の授業を見学したこともなかったので、日本語教師のモデルがいなかったんですよ。それで、これが悪いって言ってるんじゃないですけど、大学1、2年生の頃の授業って音声学であったり、日本語教育史であったり、理論的なことが多くて実践的なものがなかなか見えなかったんです。「のりかかる」と「のりかける」は何が違うのか、みたいなお題を出されてレポートを書くみたいなことをやっていて、正直これで日本語教師になれるのかなと思っていました。だから、もっと実践的なことをやっている大学がどこかにあるんじゃないかなと思って、夜に友達と飲みながら大学を受け直そうかなみたいな話をしていたんです。明確なビジョンとか情報とかがあったわけではなく、ここじゃないところに行けば何とかなるんじゃないかなみたいな感じだったんですけど。友達からは「お前がいなくなったら寂しいよ」みたいなことを言われて、踏ん切りがつかないところで、あ、インドネシアに行ってみようと思ったんです。
瀬尾ま 久しぶりにインドネシアに帰ったんですね。
加藤 ええ。2000年に祖父が亡くなったんですね。それまで入院してて、いつ亡くなるかわからないような状況で、なかなか動けなかったんです。僕が20歳になる1か月ぐらい前にじいちゃんが亡くなって、ふっと時間ができたんですね。それで、今だなと思って、10代最後の19歳のときにインドネシアに行ったんです。昔通っていた日本人学校を見て、懐かしいなとふらふらして、で、体育館に入ったら、後ろから「あれ? りんちゃん?」って声をかけられて。ふりかえったら同級生が立ってたんです。そいつはずっとインドネシアで学校に通っていて、全然連絡は取ってなかったんです。で、お互いに驚いて、「りんちゃん、何してんの?」「いや、遊びに来ててさ」「そうなんだ。バスケやる?」みたいな感じで、一瞬でふっとあの時の気持ちに戻ったんですよ。それで、インドネシアで過ごした時間が今の自分につながってるんだなって、これでいいんだって思って。ほかの大学に移ることを考えるより、今ここでやれることはやってみようと思って、オランダに留学することにしました。
瀬尾ま オランダですか!?
加藤 えぇ。オランダ南大学と京都外国語大学の交換留学が、ちょうどその年から始まったんです。インドネシアから帰ってきて、親に「俺ちょっとオランダの留学受けるわ」って言って、交換留学に応募して、3年生の後期から4年生の前期までの1年間オランダに行きました。それで、オランダで教育実習という形で初めて日本語教師として教壇に立って、日本語を教えることができたんです。これがやっぱり大きかったですね。
瀬尾ゆ 交換留学プログラムで教育実習ができたんですか。
加藤 はい。英語とオランダ語の授業は取れるんですけれど、基本的には日本語の授業をやるという感じでした。だから、学生というより本当に先生でしたよね。でも、さっきも言いましたけど、日本の大学での勉強は理論が中心で、教授法には文法訳読法とかアーミーメソッドとかがあるみたいな知識は持っているけれど、日本語の授業は見学したこともなかったんです。なのに、オランダに行って、突然「はい、じゃあ授業やって」みたいな感じだったわけですよ。だから、ものすごく緊張したのをおぼえていますね。6人でオランダに行ったんですけれども、最初の授業の前に膝を突き合わせて、「これはどうすればいいんだろう」って話し合いました。
瀬尾ま 授業のアシスタントではなく、がっつり授業をやったんですか。
加藤 そうです。授業は実習生に任せられていました。時間割の中にシフトが組まれていて、1人がメインでやって、他の学生1、2名が見学で入るという形でやっていました。定期テストも作って学習者の評価をしたりもして、本当に手探りでした。
瀬尾ゆ 初めての授業はどうでしたか。
加藤 あれは忘れもしない、2001年9月21日。これは僕の誕生日なんですけど、誕生日の日に初回の授業で、授業そのものがうまくいったかは忘れてしまったんですが、授業のあとに誕生日プレゼントをもらってすごくうれしかったのはおぼえています。それが最初の授業で、本当に手探りのまま走り出した感じでしたけど、そこに立てたのはうれしかったですね。
瀬尾ま インドネシアやオランダでの経験がなければ、もしかすると日本語教師にはなっていなかったかもしれませんね。
加藤 そうですね。オランダの最初の3か月は、やりたかったことがやれているという充実感がありました。でも、年を越した1月あたりから、いろんなことがうまくいかなくなってきたんです。授業の準備で眠れなくなったのも、その頃でした。1時、2時まで悩んでも何もアイディアが出てこない。今思えば、日本語教育の実践について何も知らないんだから当たり前ですよね。でも、そのときはどうしようって焦って、昼夜逆転する生活を送るようになったんです。だんだん最初の楽しさがなくなって、状況がどんどん悪化していくのを感じました。
当時はSKYPEもなくMSNのメッセンジャーで文字チャットしかできないような環境で、たまに中華料理店で電話カードを買って家族と話すみたいなことをしていて、自分が閉じ込められているような感じがしたんです。寮生活だったんですけど、他の人と顔を合わせたくないみたいなモードに入っていって、授業には行って外出もしているんだけど、寮にいる間はひきこもりみたいになりました。寝ないで朝6時とか7時に学校に行って時間つぶして、寮に帰ってきたら寝て、みたいな生活が一時期ありましたね。
瀬尾ゆ 最後はそんな感じで帰国されたんですか。
加藤 そうですね。最後のほうはそんな感じでうまくいかないなって思いながら帰国しました。まだ日本で大学生活が残っていたんですが、どうしたらいいかわかんなくなっちゃった感じですね。こんなのでインドネシアに行けるんだろうか、日本語教師をやっていけるんだろうか、オランダであんな体験をしたのにまだ日本語教師をやる意味があるんだろうかって、しばらく考えました。

「仲間がいるってすごくいいな」―中国で日本語を教える
瀬尾ま オランダから帰ってきてから、就職活動はされたんですか。
加藤 僕の世代は就職氷河期だったんです。同級生が、新卒の権利を残したいから進学すると言っていて、「あ! なるほど!」と。答えが出せなければ出さなくてもいいのかと思って。当時、京都外大には大学院がなかったんですが、専攻科という1年間大学に残って勉強するようなシステムがあったんです。その1年間で答えを出せばいいやと思って、そこに進みました。
瀬尾ま 別の大学ではなく、京都外大に残られたんですね。
加藤 やっぱり京都外大が好きなんですよ。そこにいた仲間も好きで、その仲間と一緒に1年間残れるなら残りたかったというのが単純にありました。大学生活の延長戦をやりたかったんだと思います。その中で日本語教育の勉強を続ければ、もうちょっと何か見えてくるかなって、なんとなく期待していたんでしょうね。
瀬尾ま それで、光は見えましたか。
加藤 自分自身でも、オランダのモヤモヤをこのままにしちゃいけないとすごく思っていたんです。京都に帰ってきて、みんながお帰り会をやってくれたときには「もう1回海外に行って、リベンジがしたい」と話をしていました。どんな形かわからないけど、もう1回行きたい。だから、専攻科に入って、先生方に「海外で仕事がないですか?」って聞いて、いろいろ応募しました。募集があるものすべてに出そう、みたいな感じで。スロバキアとかにも「英語でCVを出してくれ」って言われて、CVってなんだ? って辞書を引きながら書いて送ったら、ダメで……。でも、外大なので、卒業生がどこかしらに出て行って働いているんですよ。それで、母校に求人の相談が来るみたいで、いろいろ紹介していただきました。そのなかに「中国にいる先輩から『人がほしい』と言われてるんだけど、行く?」って言われて、「行きます!」って。その人は、京都外大を卒業して、中国の大学に日本語学部を立ち上げるために行っていました。その中国の大学に日本語教育を専門にする日本人がその人しかいなかったので、日本語教育を勉強した人を紹介してほしいという依頼があったようなんです。それで、中国に行くことにしました。
瀬尾ゆ その先輩がいる大学で教えられたんですね。
加藤 はい。中国の私立の大学でした。当時の中国の大学は、日本人が作文のクラスと会話のクラスを担当して、ほかは全部中国語ネイティブの先生がやるっていうのがスタンダードだったんですけど、先輩はそれを変えたいと。日本語の初級の授業から日本人と中国人の先生がチームティーチングでクラスを担当して教えていくことをメインにしたいと、すごく熱く語ってらっしゃって、おもしろいかもと思ったんです。
瀬尾ま 日本人はその先輩と加藤さんだけだったんですか。
加藤 それに加えて3人、計5人がいました。でも、この5人だけで何かをするということはなくて、作文の授業だったら、日本人の先生2人と中国人の先生でチームを組んでやっていました。
瀬尾ま 立ち上げの時期だから、苦労もあったんじゃないですか。
加藤 そうですね。その大学が大切にしていたのは、日本人の先生、中国人の先生、経験がある先生、ない先生、誰が担当しても同じ授業の質が保てる教案や教材を作ろうということだったんです。だから、教科書の第1課はこの人、第2課はこの人と割り振って、それぞれがたたき台を作って、1週間に1回の会議でみんなでたたき合うっていうのをやっていました。お互いに手加減をするということは一切なく、本当にバチバチやってたんです。それはしんどかったんですけど、すごく楽しかったです。「そうそう! これこれ!」という感覚が得られる空間でした。オランダの一人になっていた時期と比べると、仲間がいるってすごくいいなと思いました。
瀬尾ま イメージしていた日本語教育の世界って、仲間と一緒にやるという感じがあったんですか。
加藤 知らず知らずにそういうのがあったんでしょうね。思い返してみれば、インドネシアのスラバヤで親父の職場を見ていたときに、親父たちが同僚の先生とみんなで野球チームとかを作っていて、仕事場ってそういうふうにみんなでワイワイするところなんだろうなって思っていたんですよね。オランダのときは留学仲間ではあるけれども仕事仲間ではないわけですし、オランダの学習者も友達にはなってもやっぱり仲間にはならなかったわけですし。でも、中国ではバチバチにダメ出しもされるし、僕が思ったことを言っても受け止めてくれるしっていう状況がありました。一つよくおぼえているのは、日本文化祭というイベントのための会議を結構遅い時間までやっていて、「ああでもない、こうでもない」とみんなで言っていたんです。で、最後に誰かが「これで行きましょう」って言ったときに、「よし」ってみんなが一斉にバッと立ったんですよ。なんかそれにすごい感動しちゃって。ここに仲間がいたんだなーってすごく思ったんです。
瀬尾ま 中国でオランダのリベンジができたんですね。
加藤 そうですね。中国から戻るときには、日本語教師としてのコアになるものが手に入った感覚がありました。

「大学院に行ったらまた違う景色が見れるかもしれないな」―大学院への進学
瀬尾ま 中国には、どのぐらいいらっしゃったんですか。
加藤 3年です。
瀬尾ま お話をうかがっていると、すごくよい職場だったようですが、どうして3年で辞めてしまったんですか。
加藤 僕を拾ってくれた先輩が、名古屋大学の博士課程の大学院生だったんです。そのあとに来た人もやっぱり博士課程の院生の方ばかりだったんです。修士号を持っている人と学士だけの僕とでは、給料も任せられる業務も違ったんですね。それに、やっぱり修士号を持っている人は違うなって思うことがあったんです。例えば、教師の授業に対する学生からの評価があるんですが、1年目に僕は中国人と日本人を含めた全教師の中で最下位だったんです。だからへこんだっていうことは別になかったんですけれど、2年目に博士課程に進学している僕と同い年の人が来たんですよ。すごく仲はよかったんですけど、負けらんないなという気持ちがどっかにあったんですね。その人は最初の年から授業の評価もすごく高かったわけですよ。僕も2年目にはちょっと改善されて、何とかやっていけるぐらいの点数にはなったんです。でも、3年目は絶対に1位を取ってやろうとひそかに思って。そのためにやれることは全部やろうと、いろんなことをやりました。その結果、そいつと同率の1位になれたんです。よっしゃーという気持ちと残念な気持ちがあったんですが、もしかしたら自分も大学院に行ったらまた違う景色が見れるかもしれないなと思ったんです。で、先輩やそいつに大学院ってどんなところなのか聞いて、そいつに研究計画書も見てもらって、大学院に入るために日本に帰ってきました。
瀬尾ま なるほど。大学院はどうでしたか。
加藤 自分がそれまで体験を通して得てきたことが整理されていく感覚でした。大学院には、いろんなところで日本語を教えてきた人もいれば、日本語を学習者として勉強してきた留学生もいたんですが、みんながそれぞれの経験を共有して、あのときのあれってそうだったんだみたいな感じで体系化されていくのがすごく楽しかったです。それに、「それは違う」「いや、違ってないよ」って、お互いに活発にやりとりをして、中国にいた時みたいな何でも言い合えるような場所で、すごく楽しかったです。
瀬尾ま 中国の経験を再び、みたいな感じですね。
加藤 僕の指導教員も歯に衣着せるほうじゃないので、言いたいことはバシッと言ってくれたし、それに周りも感化されて、どんどん意見が出てくるようになって楽しかったです。修士1年の夏休みなんか、塾で講師のアルバイトをしていて、それ以外の時間はずっとパソコンに向かって文字起こしをしているような生活だったんですが、それもすごく楽しくて。自分がやっていることに意味があるというか、みんなと話しあっていることにつながっているのかもしれないっていうワクワク感がありました。
瀬尾ゆ どんなことを研究されていたんですか。
加藤 海外の日本語学習者って、教室外で日本語母語話者と話すことがあんまりないんですよね。ロールプレイで会話を疑似体験させるような活動が結構あると思うんですけれど、考えてみたらそれってすごくおもしろいことで、母語はまったく同じなのにお互いに日本人のふりをして、日本語を話しているわけですよね。そこにどんな効果があるんだろうって思って、ロールプレイの場面をビデオに録画して、どんなフィードバックが起こっているのかを会話分析の手法で明らかにするということをしました。
瀬尾ま 修士を取られてからは、どうされたんですか。
加藤 博士課程に行こうとは思ったんですね。でも、指導教員の先生が他の大学に行っちゃったりして、なかなか名古屋大学で会話分析の研究を続けていくのが難しくなったんです。どうしようかなって迷いながら、ぼんやりした感じで博士の入試を受けたんですが、やっぱりダメでした。それで、日本人向けの塾の講師をやりながら、次どうしようかって考えてました。塾の講師って生活を成り立たせることはできても、自分がやってきたものとは違うので、やっぱり日本語を教えるところが一番だよな、将来は大学院に戻るにしても、まずは日本語を教えなきゃと思って、NIHON MURAの求人を見ました。そして、いろんなところに履歴書を送って、日本語学校の専任になりました。
瀬尾ま 海外で働こうという気持ちは、もうなかったんですか。
加藤 それは正直なかったですね。そのときは妻と結婚しようと考えていたので、あんまりふらふらしないほうがいいかなと思って、日本で就職しようって考えていました。妻は、実は中国の大学で出会った同僚なんですよ。
瀬尾ま え? 日本語の先生なんですか。
加藤 僕なんかより優秀な先生で、結婚するときは学部長に「お前は自分が辞めるだけじゃなくて、この子も連れていくのか」と言われてしまいました。それで、妻を日本に呼べるだけの経済力が必要でした。要は定職があって、在職証明書が出て、妻のビザがとれるようにすることが一つの目標になっていました。今にして思えば経済的にそんなに余裕があったわけじゃないですが、一人だと厳しいけど二人で働けば生活できるかもみたいなのはありました。最初は妻もスーパーでアルバイトとかして、そのうち中国語の先生も始めて、それなりに「名古屋、楽しいね」ぐらいにはなりましたね。
瀬尾ゆ 日本語学校ではどれぐらい働かれたんですか。
加藤 名古屋では2つの学校で働きました。最初のところで2年、2つ目のところで2年です。
瀬尾ま 学校を移られたのは、ステップアップのためですか。
加藤 このときの転職はそうです。妻が日本に来て、もうちょっと収入が増えればうれしいし、自分の基盤となるようなところに行ければって思っていたところに、同じ名古屋市内で求人が出ました。それで、無事に雇っていただいて転職したんですけれども、その学校は、ちょっとこれは自分の未熟さのせいなんですけど、いろいろなミスが積み重なって、やめたっていうよりは自分のなかではクビになったぐらいの気持ちで捉えているんです。
瀬尾ゆ いったいどうしたんですか。
加藤 ちょうど子どもが生まれたりして、少し大変な時期だったんです。子どもが夜泣きして奥さんも早く休みたいだろうと思っても、こっちが授業準備とかでいっぱいいっぱいだと、なかなか助けられないっていうジレンマがあって……。妻もしんどかったと思うんですよね。それで、妻の両親に子どもをまだ会わせてなかったので、子どもが1歳になるぐらいのタイミングで1回中国に帰ったんです。その飛行機が出発して数時間後に、僕のおばあちゃんが亡くなったっていう電話が来たんですよ。それで、僕は実家がある茨城に戻ったんですけれども、そこで代講の時間の割り振りを間違えてしまって……。それで教務主任からそれまでにあったいろんなことも含めて指摘されて。職場内でも孤立するような感じになってしまったんですよね。で、このまま名古屋で子どもを抱えて3人でやっていくよりは、実家に戻ったほうがいろんなケアを受けながら生活ができるんじゃないかなと思って、実家の近くで求人を探していたら、たまたまあって、茨城の日本語学校で教務主任として働くことにしました。

瀬尾ま 茨城に戻られたんですね。
加藤 お給料的にはちょっと下がってしまったんですけれども、おばあちゃんが亡くなって、おばあちゃんの家が空いていたので、そこから通うことにしました。
瀬尾ゆ 教務主任になられて、いろいろと見える世界が変わってくると思うんですが、そのあたりはいかがでしたか。
加藤 結論から言うと、楽しかったです。そこは僕よりも経験がある先生がいなかったんですね。それで、カリキュラムの組み方とか進路指導の仕方とか、多少なりとも自分の経験が必要とされたところはすごく救われた気持ちになりましたね。そして、みんな本当に一生懸命だったし、誰一人偉ぶる人がいなくて、本当になんでも言い合える仲間が集まってたと思うんですよね。
瀬尾ゆ やっぱり同僚関係っていうのが加藤さんにとって大切なんですね。
加藤 そこではちょっと息を吹き返した感じがありました。また仲間ができたっていう感じでした。その中の一人はその後大学院に行きたいってことで、いろいろと話したんですが、そのときに「日本語教育のことは加藤先生のやり方を見ていろいろと学ばせてもらった」と言われました。なんか僕が中国にいたときのライバルの奴のようなところに、もしかしたら自分も来ているのかなって思いましたね。
「自分が声さえ上げれば、日本語教育に関心を持ついろんな世界の人とつながれる」―研究者の道に
瀬尾ま どうしてそんないい職場から転職されたんですか。
加藤 そこにずっといることもできたんですけれども、京都で大学の同期がかかわっている研究会があって、そこに出てみたんですね。京都に行く口実にもなるし。そしたら、みんながバチバチとやっていて、これだよなと思ったんです。自分は教務主任になることができたし、そこにいい仲間もいるし、これからもやっていけるような気もしていたんですけど、研究会に参加して、まだあるじゃんって思っちゃったんです。そういった研究の世界に行かないで今のままで本当にいいのかなって思ってしまったんですよね。それで、茨城に帰って、いろんな求人に応募してみたら、前職の国際医療福祉大学に声をかけてもらって、研究者の道に行けることになったんです。
瀬尾ゆ 研究会で見た研究の世界には、何が見えたんでしょうか。
加藤 自分がほしかったのは、その日本語学校のような雰囲気があたたかくて、みんなでがんばろうっていう感じだったのは確かなんです。ただ、研究の世界は厳しい環境の中で何かを突きつめていくような世界で。日本語学校では授業をやって学生と話して、家に帰って寝て、そして次の日に学校に行ってみたいな、ある程度こなすようになっていたんです。螺旋階段みたいに上がってきていたけれども、螺旋が上じゃなくて横に回り始めている気がしたのかもしれません。もうちょっと上に行くためには環境を変えて、自分が叩かれて、傷つくかもしれないけれども、それ以上に得られるものがあるような気がして、そういう世界に行かないと、たぶん人生ここで終わるんだろうなって思ったんです。
瀬尾ま 加藤さんのresearch mapを見ると、大学で働き始めてから発表や論文が増えていますね。やはり意識の変化があったんですか。
加藤 自分の研究を聞いてくれる人がいるということは、本当に喜びだと思っています。僕は院生のときの学会発表は社会言語科学会でやった1本だけなんですけど、何年かあとに「発表を聞いてました」と言ってくれる人がいたり、今でも「論文読んでます」と言ってくれる人がいるんです。そういう人がいると、自分のやったことが遠くまで届いている感じがして、世界が広がった感じがします。
瀬尾ま 職場の仲間だけではなく、発信してどんどん仲間が外に広がっているという感じなんでしょうか。
加藤 職場で仲間ができるかっていうのは、それこそ「職場ガチャ」じゃないですけど、運も大きいと思うんですよね。でも、研究の世界に来て思ったのは、研究の世界では自分が作ろうと思えば仲間ができるってことです。
僕がやっている研究はいくつかあるんですが、一つは糧ラボと言って、教師のキャリア研究をやっています。一緒にやってる奴は京都外大の同級生で、自分の「いつか何かやりたいね」っていうことばをずっと本気にしてくれていて、僕が研究者になったときに、自分たちのための研究をしようということになったんです。それで、大学に入学したときに「日本語教師は食べていけない」と言われたけれども、自分たちは食べてこられたから、それを何らかの形で残さなきゃいけないよねって言って始めたのが糧ラボなんです。
瀬尾ゆ 学生時代の仲間と研究を始めたんですね。
加藤 もう一つは会話分析の研究グループを作っています。何年か前の日本語教育学会で会話分析についての発表をしたんですが、そのときに発表したことについてTwitterでおもしろいねってコメントをもらって。僕も自分ひとりでやることの限界を感じていたので、「誰か一緒にやりませんか」って呼びかけたんですね。それでSlackで6、7人くらいでやっている会が、ずっと続いています。ほかにも、前任の大学の同僚と看護師を目指す留学生のための教材開発を、科研費を取ってやったりしています。自分が声さえ上げれば、日本語教育に関心を持ついろんな世界の人とつながれるっていうのは、研究者になって一番よかったなって思います。
「マジョリティが、僕らが変わらなくちゃだめだ」―研究者として目指すこと
瀬尾ゆ 研究の関心は日々の実践から生まれてきているんですか。
加藤 そうですね。大半は必要に迫られてやったことや、自分のことの延長線上が多いですね。ただ、さらにそこを飛び越えたいなと思っています。さっき、いろんな人とつながったと言いましたけど、結局は日本語教育関係者が多くて……。例えば今、創設される公認日本語教員制度や日本語教育機関の認証制度についてみんなで話そうという会をやったりしているんですが、やっぱり日本語教師しか来ないんですよね。本当は学習者にも来てほしいし、学校の教員とか、それこそ市役所や看護師の人とか、いろんな人が集まる場所がないといけないなと思っているんです。だから、自分がもっと社会につながっていかなきゃいけない。今までは、よい仲間を得て、よい組織の中でよい関係性があって、一緒にやりあえて楽しかったんですけれども、もっと広い範囲の人とそれができたら、すごく自分は幸せだろうなと思うんですよね。
瀬尾ゆ どのようにして、そう思うようになってきたんでしょうか。
加藤 2つあるかなと思います。1つは前任校で看護師と接することが多かったことです。EPA(経済連携協定: Economic Partnership Agreement)の枠組みで日本に来て看護師をやる外国人は多いんですが、日本の大学に留学して日本の看護師の国家資格に合格して日本で働こうというケースは多くないんです。なので、看護学の先生方はそういう留学生を教えた経験が少ないわけですよ。そうすると、先生も「日本語が全然できないのに、どうしたらいんですか」って戸惑ってらっしゃってて、留学生も大変な思いをしているのかなと思ったんです。
2つ目は、会話分析をして感じたことです。さっき言った会で、ある記者会見の場面について会話分析をしたんですね。外国人の記者が外務大臣に日本語で質問をしたら、「What do you mean?」って英語で聞き返して「日本語、わかっていただけましたか」って記者の日本語能力を確認する発言をしたんです。それで、その行為が差別じゃないか、と問題になっていて。外務大臣本人は「差別という意図はなかった。誤解を与えたなら謝罪します」みたいな、よく聞かれる言い訳の謝罪をしたんです。これ、本人には差別っていう意識は本当にないんだと思います。ただ、構造的にそういう差別構造ができあがっているんですよ。それに、Twitter見たり、いろんな人の会話を聞いたりしていると、その端々から、マジョリティの権力がマイノリティにどれだけ残酷なことをしているのかって思うようになってきたんです。僕は今まで日本語教師としてマイノリティである日本語非母語話者とかかわってきたわけだけれども、なんでその人たちが変わらなければ社会に参画できないんだろうと思い始めたんですよね。

例えば、医療現場の会話分析をやるきっかけになったのも、前任校でおなかが痛くて油汗をかいている留学生がいて、車に乗せて病院に駆け込んだんですよ。痛くて吐いて、顔も真っ青で、お医者さんに見せたら、お医者さんが「この人は日本語がまったく話せないし、外国人だから顔色を見ても痛いかどうかわからないから、診れません」と言うんです。そんなの絶対におかしいと思って。そんなにお前ら偉いのかよって。だから、日本語を教えて、外国人を社会に参画させようというのは、ものすごい傲慢なことをしているんじゃないかなと思うようになったんです。だけど、日本語を学ぶことが必要ないとは思わなくて、社会で自分らしくいられるための手段として言語を持つということは大切だとは思うんです。でも、そのためにはマジョリティが、僕らが変わらなくちゃだめだし、その力が僕たちにしかないんだとしたら、まず僕らが動くべきだよなと思ったのが意識が変わった経緯ですかね。研究者の立場にいれば、今までいた立場よりも社会を変えることができるかもしれないと思っています。自分のマジョリティ性が持つ力を、差別のためではなく、社会を公正にするために使っていきたい。それを、これから目指していきたいんです。
「日本語教育は何のためにあるのか、さまざまな人と考え語り合おう」―加藤さんからのメッセージ
瀬尾ま 最後に、今から日本語教師になりたい人やキャリアの浅い人たちに向けてメッセージはありますか。
加藤 私が最近日本語教育関係で感動したのは、先日行われた登録日本語教員や日本語教育機関の認証に関するパブリックコメントの資料を読んだときです。20代から70代以上までの多様な方々が、「この社会において日本語教育とはどうあるべきか」について900件以上の意見を寄せているんですね。コメントは書かれたそのままの形では公開されていないですし、賛成できない意見ももちろんあるんですが、それでも日本語教育について真剣に考えている人たちがこれだけいるんだ、というのは、自分がそれに関して小さいイベントをやっていたこともあって、ちょっとぐっときましたね。ただ、「で、給料は上がるの?」というところに議論が終始してしまったりすることも少なくないんですが……。もちろんそれも大事なんですけどね。でも、「別に何も変わらないんじゃないの?」という冷笑や無関心で終わらせちゃいけないと思うんです。日本には現在移民政策と呼べるものがないのですが、その中で日本語教育業界は多くの理念を打ち出しています。どうしてもキャリアの初期には「どう教えればいいのか」とスキルについて考えることが多いと思いますが、それだけではなく、「日本語教師は何のためにいるのか」「日本語教育は何のためにあるのか」について、日本語教師だけでなく、さまざまな人と考え、語り合ってほしいと思います。そこに経験やスキルの差はありません。その議論を背中合わせに共有して、それぞれのフィールドで実践を重ねていくことができれば、日本語教師と日本語教育ができることはもっと広がっていくはずです。私も日本語で食べてきた一人として、みなさんが戦う背中を預けられるようになりたいですし、教育、研究、それから生活の実践を通して、いっしょにいい社会を作っていきたいですね。
==============================
インタビューを終えて
瀬尾ま 仲間を作っていくこと、とても大切だと思います。そして自分自身も仲間がいたからこそできたことがたくさんあったなと思い返していました。そういった仲間、同僚もそうですが、加藤さんのようにTwitterなどのソーシャルメディアを使って作ることもできるなと思います。この『日本語教師の履歴書』の読者もどんどん仲間を作っていってほしいなと願っています。
瀬尾ゆ 日本語教師は日本語教育の垣根を飛び越えていく必要がある、というご意見に深く頷きました。そして、それは大それたことをしようと難しく考えるのではなく、身の回りの人たちに日本語教育や日本語教師の仕事について話してみるというところから気軽に始めることができるかもしれないなと思いました。
